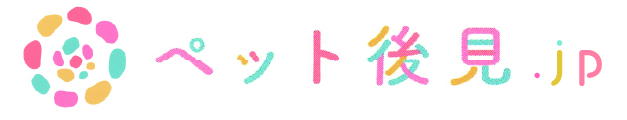最期までペットと安心して暮らせる仕組みづくり・サービス提供をしています。
現在、日本では一年間に約10万頭犬猫が保健所に持ち込まれています。中でも、高齢の飼い主さんが、入院や要介護になったことで飼えなくなってしまうことは年々増え続けています。
「飼えなくなってしまうかもしれない。もし、自分が飼えなくなった時、それでもこの子を幸せにしてあげたい。」
ペット後見互助会とものわは、殺処分問題に取り組む奥田順之獣医師が発起人となり設立された互助会です。トレーナー、弁護士、行政書士、高齢者支援専門のファイナンシャルプランナー、老犬老猫ホーム等と連携し、犬猫と飼い主さん双方が最後まで幸せに、安心して暮らせる選択をサポートをしています。
高齢者でもペットと暮らせるようにするための『ペット後見』
ペット後見とは、飼い主が入院や死亡などにより、万が一ペットを飼えなくなる事態に備え、飼育費用、飼育場所、支援者をあらかじめコーディネートしておくことで、飼えなくなった場合にも、最後まで飼育の責任を果たすための取り組みの総称を指します。
ペット後見に取り組む事業者は全国に複数存在します。岐阜を中心に活動する当団体(NPO法人人と動物の共生センター:代表奥田順之(獣医師))は、主に東海三県を中心に石川、富山、滋賀、京都、大阪等からも相談を受け、ペット後見の対応を行っています。
当団体では、ペット後見互助会とものわを組織し、会員にもしものことがあったら、引取り、新しい飼い主を探すというサービスを展開しています。
お気軽にお問い合わせください。058-214-3442受付時間 9:00-17:00 [ 月・火除く ]
お問い合わせ自己責任から共助の世界へ。コミュニティによる引取りと譲渡を目指して。
子どものいない高齢者世帯が増加している昨今、高齢者がペット飼育を行う上では、ペットの将来を親族に任せるというこれまでのやり方が通用しなくなってきています。
「親族がいないなら、ペットを飼わなければいい」
という声もありますが、ペットと暮らすことを生きがいに、心の支えにしている方も少なくありません。親族がいない、後見人がいないというだけで、ペットの飼育にNGを出す権利は誰にもありません。
ペットを飼いたい、一緒に暮らしたいという気持ち、それは幸せを追求しようとする気持ちです。実質的に誰も止められないですし、実際に飼えなくなってしまっている人が多く発生している今、自己責任で、「飼いきれないなら飼うな」と主張するよりも、社会全体で共助の仕組みをつくり、万が一の時に、支え合えるようにする方が現実的と言えるでしょう。
ペット後見互助会とものわは、そうした共助の気持ちをベースにしたサービスになっています。
高齢だから飼育をあきらめている人が、保護犬猫の引き取り・預かりの担い手に
一方で、飼いたい気持ちがあり、現在は健康で自立した生活ができており、十分にペットを飼う余裕があるにも関わらず、自分の年齢から最後まで飼える自信がなく、飼うことをためらっている人もいます。当団体では、こうした方に向けて、ペット後見のもう一つの形である、保護犬猫の生涯預かりを『ずーっと預かり制度』の構築に向け、動いています。
今ペットと一緒に暮らしている方も、これからペットと暮らしたいと考えている方も、皆それぞれの状況の中で、飼えなくなるリスクを持っています。ずーっと預かり制度を活用することにより、もしも飼えなくなったときに、制度に参加する多くの飼い主さん同士で引き取りと譲渡を行うなど、コミュニティで支え合えるようにすることが理想と考えています。
ペット後見を成立させる、3要素
ペット後見を行う上で必要な要素は、①飼育費用を遺す方法、②飼育の受け皿、③万が一の際に緊急保護ができる見守り体制の3点です。
飼育費用を遺す方法
①飼育費用を遺す方法には、遺言、生命保険、信託などがあります。
ペットの飼育費用を遺す方法としては、ペット信託が有名ですね。ペット信託は、民事信託を活用して、信託契約を作成し、受託者の管理の元、信託財産をペットの飼育のために使う枠組みである。
そのほか、生命保険を活用した方法では、プルデンシャル生命とプルデンシャル信託が、生命保険信託という商品を出しています。これは、生命保険金を信託財産として、認定NPO法人などの公益的な団体を受益者(財産を受け取る人)に設定できるものです。当団体でも、半分くらいの契約者の方が、生命保険信託を使っています。
相続人がいない、あるいは、相続について早めに整理しておきたい、動物のために遺産を活用したいというニーズがある場合、遺言により飼育費用を遺す方法もお勧めです。
飼育の受け皿
②飼育の受け皿としては、ペットホテル、老犬老猫ホーム、保護活動を行っているNPOなどが含まれます。終生飼育が可能な施設は必ずしも多くありませんが、飼育費用をしっかり残すことで、引き受けていただける施設の幅は広がります。動物の飼育には費用も人手も必要です。安価に抑えようとせずに、適切な飼育費用を遺すことが大切です。
飼育の受け皿を決めるにあたっては、一番大切なことは、飼い主さんとの信頼関係です。直接施設に訪問でき、スタッフの様子や、世話の様子をみて、納得できる施設に預けるべきです。大切なわが子をお願いするわけですから、遠方の、行ったこともないような土地の施設に任せるのではなく、地元の顔の見える業者を優先するようにしましょう。
見守り体制
③万が一の際の緊急保護ができる見守り体制も重要です。いざ、入院が必要になった、事故に遭ったということがあった場合に、ペットが家に残されていたら、ペットの命に関わる事態に発展してしまいます。
②の飼育の受け皿となる事業者が駆けつけてくれればよいのですが、遠方の事業者に依頼している場合、緊急保護は難しいかもしれません。やはり、近隣のいつもお世話になっている事業者に依頼し、いざという時にすぐ動いていただけるような体制を整えておくことは重要ですね。
また、普段からペットシッターを利用しておくと一番確実です。ペットホテルの場合お迎えをやっていない場合があります。シッターさんにお願いすることで、ペットもいつも世話してくれている人ですから、安心して過ごすことができます。
ペット後見互助会とものわでの対応
ペット後見互助会とものわでは、この①~③のコーディネートを切れ目なく行うサービスを展開しています。当団体は、代表が獣医師、理事に弁護士と医師がおり、動物・法律・福祉の側面から、サポートを提供できることが強みだと考えております。
全国での対応
①、②、③すべての要素を一つの事業者が担うことはなかなか難しいですが、それぞれ個別の事業者が担うことは可能です。当団体では、そうした一部分を担える事業者と連携関係を築き、協働してペット後見を提供できる体制づくりを進めています。
事業者向けのペット後見共同学習会を月1回実施しています。連携に興味のある事業者の皆様はぜひご参加ください。
ペット後見互助会『とものわ』による支援内容
ペットの飼育困難に備えるための個別相談
どうしてもペットを飼えなくなってしまうということは、家族・親族も関わる、家族の大きな出来事になります。もちろん、自分たちで飼い続けられるようにすることが第一ですが、独居や夫婦のみのご高齢家庭の場合で、ご家族に飼育を頼めない事情があることもあります。
それぞれのご事情を1時間ほどお伺いし、対応策を検討し、コンサルテーションいたします。担付生前贈与、負担付遺贈、遺言、民事信託、商事信託、生命保険信託、老犬老猫ホームなど、様々な選択肢があります。ご家族の年齢・健康状態、ペットの年齢・健康状態、ペットのしつけの程度など様々な要因が影響してきます。複数の選択肢の中から最も適切な計画を具体的に立案します。最も適切な方法を一緒に考え、最適な選択ができる様にご助言いたします。
個別相談料:無料
※代表の獣医師奥田がご対応いたします。
※まずは、TELにてお問合せください(058-214-3442)
◆専門家の紹介と契約作り
個別相談を通じて作った、将来計画を実行するためには、ペットのための財産を遺す・託すための契約作りと、実際にペットを飼育してもらう受け皿となる人・組織との契約を取りまとめる作業が必要になります。契約作りは、とものわサポートメンバーである弁護士・行政書士等の士業が、ペットの飼育については、同じくサポートメンバーである老犬老猫ホーム・シェルター関係者と連携し、契約作りのコーディネートを致します。
◎ 契約作成料:実費
※契約内容によって作成料は変化します。別途見積もりを作成いたします。
◆ペットの引き取りと新しい飼い主への譲渡
作成した契約に基づき、ペットを引き取り、次の飼い主へのバトンパスを行います。どのような契約を作成するかによって、シェルターで引き取り預かりながら新しい飼い主を探したり、老犬老猫ホームで終生世話をしたり、親類知人が飼育することのサポートをさせていただくなど様々なパターンが考えられます。
お気軽にお問い合わせください。058-214-3442受付時間 9:00-17:00 [ 月・火除く ]
お問い合わせ高齢者によるペット飼育の現状と課題
超高齢社会を迎え、社会保障給付費は平成 28(2016)年度は 116兆 9,027億円と高齢者関係給付費は 78兆 5,859億円となり過去最高の水準となった。2025年まで続く75歳以上人口の急激な増加は、介護需要を大幅に増加させ、生産人口の減少と相まって、介護需給バランスの崩壊という課題をもたらしている。この課題の解決に向けては、介護人材の確保と同時に、高齢者の社会参加を促し、健康寿命を延ばし、地域に根差して自立生活を送る元気な高齢者を増やすことで、介護需要を下げることが必要である。こうした視点から、厚生労働省は「健康寿命延伸プラン」を発表している。
介護需要を下げる政策には様々なものがあるが、動物の飼育・アニマルセラピーの効果は、この課題に有効に作用する可能性がある。動物飼育の生理的な効果としては、心血管疾患のリスクの低下や心疾患後の寿命の伸長、心理的効果としては、孤独感の減少、うつ状態や不安の軽減、幸福感・生活満足度の向上などが挙げられる。社会的効果として、活動性の増加、社会的ネットワークの広がりなどが報告されている,。
星ら(2018)は、在宅に居住する高齢者における犬猫を世話することと要介護度の因果構造を明確にすることを目的に、九州A自治体で、在宅居住する高齢者全員を対象(分析対象5,022 名)とした調査を実施している。研究では、年間収入額が犬猫の世話をすることに関連し、犬猫の世話をすることで主観的健康感を高め、外出頻度を維持させることを経て、最終的には死亡を含む「要介護度」を抑制するという因果モデルの適合度が高く、このモデルが、男性の死亡を含む「要介護度」の13%を説明でき、女性では15%が説明できると結論付けている。つまり、犬猫の飼育は、間接的に要介護度抑制に影響を与えていると言える。
さらに、経験的な話ではあるが、動物を飼育している高齢者は、動物を最後まで面倒を見なければならないという責任感から、自身が要介護状態になっても、施設に入所せず自立した生活を送ろうとするモチベーションが高い。実際にこれまでの相談例の中でも、要介護3の独居状態でありながら、ペットとの暮らしのために、自立生活を続けている高齢者もいる。高齢者が動物を飼育することは、健康寿命を延ばすだけでなく、地域での自立生活への意欲を後押しする要素になると考えられる。
しかし、「最期まで面倒を見なければならない」という責任感は、飼育を阻害する要因にもなっている。平成30年度、全国の行政が飼い主から引き取った犬猫の数は、14,176頭であるが、保健所等に持ち込まれる犬猫の30~50%は、飼い主の入院・死亡によるものである,。この約半数は飼い主の入院・死亡によるものと考えられる。現在犬を飼育していない70代のうち、33.6%が「最後まで世話する自信がないから」を飼育しない理由に挙げており、このリスクが、飼育を阻害する要因になっている。また、保健所や動物保護団体は、高齢者への譲渡を制限していることが少なくない。これは、高齢者が、自分の年齢に見合った中高齢のペットを迎えることを阻害し、高齢者のペット飼育の可能性を減少させる要因になっている。
仮に、高齢者世帯が、ペットを飼育できる環境にあっても、ペット飼育をしないのであれば、要介護度の抑制という効用を得ることはできない。飼育困難に陥るリスクを下げ、飼育困難になっても動物の命に対する責任を果たすことのできる仕組みを構築し、飼育に対する安心感を高める仕組みを構築できれば、休眠資源である『動物が人を癒す能力』を活かし、『動物のために人が自立して生活しようとする力』を引き出し、介護需要を下げ、地域で最後まで生活する社会の実現に寄与することができると考えられる。
ペット後見の社会的インパクト
ペット後見の主な受益者は、①現在ペット飼育をしている高齢者のみの世帯、②今後ペット飼育を希望する高齢者のみの世帯である。
高齢者のみの世帯で、別居の子どもがいない世帯は、単身世帯で6,559千世帯×25.7%=1,686千世帯、夫婦のみ世帯で7,526千世帯×9.7%=730千世帯、合計2,416千世帯である,。
①現在ペット飼育をしている高齢者のみの世帯は、2,416千世帯×18.3%(70代飼育率)=442千世帯であり、これが、本事業の主たる対象となる。さらに、②今後の飼育意向のある高齢者世帯まで広げると、70代の今後飼育意向は、犬猫合計で27.0%に上り、同様の計算から、652千世帯となり、合計で1,094千世帯が本事業の潜在的な対象となる。
これらの世帯が、飼育困難に陥るリスクを気にすることなく、犬猫を飼育できるようになれば、78.6兆円を超える高齢者関係給付費のうち、年金(54.3兆)を除く、医療・福祉分野の費用24.3兆円を圧縮できる可能性がある。Siegelらの研究(1990)では、犬飼育者は、非飼育者に比べ、年間の通院回数が平均で1.19回少ない結果が報告されている(右図参照)。鈴木ら(2013)の研究では、高齢者施設にアニマルセラピーを導入した場合の医療費削減効果について、全国で1351.3億円の削減につながると推計している。
ペット後見の普及により、高齢者世帯でのペット飼育が社会保障費削減や、高齢者が地域で生活する社会の実現に与えるインパクトが、どの程度になるかについては、現段階では十分な評価はできていないが、今後大学などの研究機関と共に可能な限り精緻な評価を行うべきと考えている。
これまでの主なセミナー実績
2016年
- 高齢者とペットの共生セミナー~最後まで一緒にいたいから~ 主催:愛犬の命を守るフェス
- 平成28年度千葉県動物愛護セミナー「高齢者とペットの共生を考える」 主催:千葉県
2017年
- 飼えなくなるその日に備え、今、できること 主催:人と動物の共生センター
2018年
- ペット後見互助会の仕組みと活用法(10月3日/12月10日)
- 大切なペットのために~60歳からのペットの飼い方セミナー~(11月22日)
2019年
- もしも、飼えなくなったときにペットに安心を遺すためには(7月22日)
- ペットのための生命保険勉強会 主催:人と動物の共生センター(6月11日)
2020年
- もしも、飼えなくなった時にペットに安心を遺すためには(1月29日、2月27日)
- ペット事業者向けセミナー(オンライン)(3月10日)
- ペット後見共同学習会 4月から毎月1回 第4火曜日開催